こんにちは。ikio(@ikio04731250)です。
実家の相続農地を使って「農業 × 商品開発」に挑戦中です。
農地も立派な資産。これも不動産投資(資産形成・活用)の一環として活かし、収益化するプロジェクトを進めています!
この取り組みの始まりはこちらの記事から。
▶「農業はじめました」不動産投資の新しい挑戦
相続予定の農地活用を検討した記事を書きました。
▶「農業はじめました」不動産投資の新しい挑戦
いろいろと可能性が広がりそうなこともあり、結論として、自分で耕作する事にしました!
・圃場の確認 ←今回はここ
・土壌改良
・定植前の準備
・定植
という感じで、項目ごとに記事を分けて書いていきます。
さて、「耕作する」と簡単に言っても、まずは圃場の現状を把握する必要があります。
また、親世代が使っていた農機具類が今も使えるのかどうかも気になるところです。
まずは自宅からgoogle mapで確認してみます。
あれ? 思ったより整備されてる・・。
親が体調崩して、少なくとも6~7年は手を入れてないはずですが、草木もそれほど伸びていません。
後日わかったのですが、地域の組合が写真奥の土手を野焼きする際に、ついでにこの圃場も焼いてくれていたそうです。これは本当に助かりました!木が生い茂ってしまうと、耕作できる状態に戻すのにとんでもない手間とコストがかかりますからね。
ちなみに、野焼きは原則として違法です。ただし、農業を営むために行う焼却(ゴミ焼却を除く)は、例外として市に認められているケースがあります。とはいえ、この地域は農業振興地域で、周囲に住宅も少なく、苦情も出にくいため、実際には“グレーゾーン”のような形で成り立っている印象です。
さて、次は実際に現地を訪れてみます。ここに来るのは数十年ぶりでしょうか。
小学生の頃のかすかな記憶では、畑として使われていて、ジャガイモやタマネギなど、手間の少ない作物を育てていたように思います。
今思えば、親もサラリーマンをしながら兼業農家をしていたので、作物の選び方にも理由があったんですね。
桜も咲き始めの4月上旬に訪れました。晴れの日が続いており、土はいい感じに乾燥していました。
ちょうど3月頃に野焼きされたようで、圃場には灰が少し残っていました。この灰は土の栄養になるので好都合です。ただし、土中に残っていた雑草の根はまだ健在で、暖かくなってきたこの時期には、早くも新芽が顔を出していました。
圃場の周囲には遮るものがなく、風通しや日当たりも良好。倒木もなく、石もごくわずか。いいスタートが切れそうな予感!
とはいえ、長年耕作されていなかったため、土はかなり固くなっていました。土を柔らかくすることに加えて、灰を混ぜ込み、雑草の根を取り除く必要があります。一度トラクターでしっかり耕す必要がありそうです。
google mapで確認した圃場。野焼き直後のため、全体的に灰が広がっている状態です。
続いて農機具の確認です。
鍬(くわ)やレーキなどのシンプルな農具は問題なく使えそうでした。鍬なんて、おそらく50年以上使っていると思いますが、鉄製の道具は本当に丈夫ですね〜。
一方で、比較的新しいはずの小型管理機は、メーカーでのメンテナンスを受けないと今期の稼働は難しそうでした。長期間放置していた機械は、そう簡単には動いてくれませんね。
幸い、組合管理の大型トラクターを借りられることになり、先述の耕運作業はそちらで対応できました。・・が、この先はすべて手作業になるので、ここからが“地獄の始まり”ですw その辺りは、また別の記事でまとめようと思います。
圃場の広さを決める
宅地なら登記簿謄本や公図で確認しますが、農地の場合は「eMAFF全国農地ナビ(農林水産省)」で、農業台帳に登録されている一部の情報を確認できます。これは全国網羅しているので、ご自身の地域を確認してみてください。今回はそこから「地積(面積)」をチェックしました。
この圃場は340㎡で登録されていました。
無理ではありませんが、今期すべてを使うのはさすがに大変。これは何か新しいことを始めるとき全般に言えることですが、まずは「小さく始める」のが基本です。
というわけで、今期は100㎡にに絞って計画を立てました。
340㎡のうち、100㎡は比較的区画しやすそうですが、不整形地のため畝(うね※)のレイアウトがポイントになります。以下のように事前に計画を立てました。
※畝(うね)とは、圃場の中で作物を植える為盛り土をしている部分。
・畝:80cm×170cmを4つ(約54.4㎡)
・作物:サツマイモ
・種苗数:200株
・作付け:株間30cm
耕作面積はやや控えめですが、
①畝と畝の間や周囲に通路を確保する必要があること(幅30cm以上ほしい)
②土壌改良に余裕が必要
これらの理由から、耕作面積を設定しました。
また、雑草の根を手作業で取り除く必要もあるため、作業量は軽めに設定しています。アラフォーの体力がどこまで保つかも未知数ですしねw
まずは圃場の現状復帰!
繰り返しになりますが、耕作されていなかったため土は固く、柔らかくするための耕運、灰の混合、雑草の根の除去が必要です。
まずは、大型トラクターで一気に耕土していきます!
作業自体は機械の力もあって1時間ほどで終わるのですが、圃場内にはこぶし大の根がゴロゴロと残っています。これらを放置すると、畝立てや整地の際にレーキに絡んだりと、非常にやっかいです。
根は土が絡んでいるため、手で拾いながら土を落としていく作業が続きます・・これが本当に大変(腰にもきます)。
ちなみに、鍬などで手作業する場合は、しばらく雨が降っていない“乾いた状態”で行うのがコツです。
湿った土は重く、体力の消耗が倍増します。
ある程度根を取り除いたら、次は畦道(あぜみち)の除草。
まだ寒さが残る時期なので、軽く除草剤を撒いて枯らしておけばOKです。
まとめ
土を耕し、根を取り除いた結果、圃場は柔らかく良い状態になりました。
今回は休耕期間が長かったこともあり、痩せた土地でも育ちやすいサツマイモを選びましたが、来期にはもう少し他の作物にも挑戦できそうです。
いや~しかし、久しぶりの土いじりは大変ですが、それ以上に楽しいと感じます。
土の匂いを感じながら作業していると、宮崎駿監督の名作『天空の城ラピュタ』の名セリフ「土から離れては生きられないのよ。」が、何度も頭をよぎりますw
・・まぁ、シータはそんな感傷的な意味で言ったわけではないのでしょうがw
以上が圃場確認から初動作業までのレポートでした!
次回は「土壌改良」についてまとめていきます。
今回は以上です。
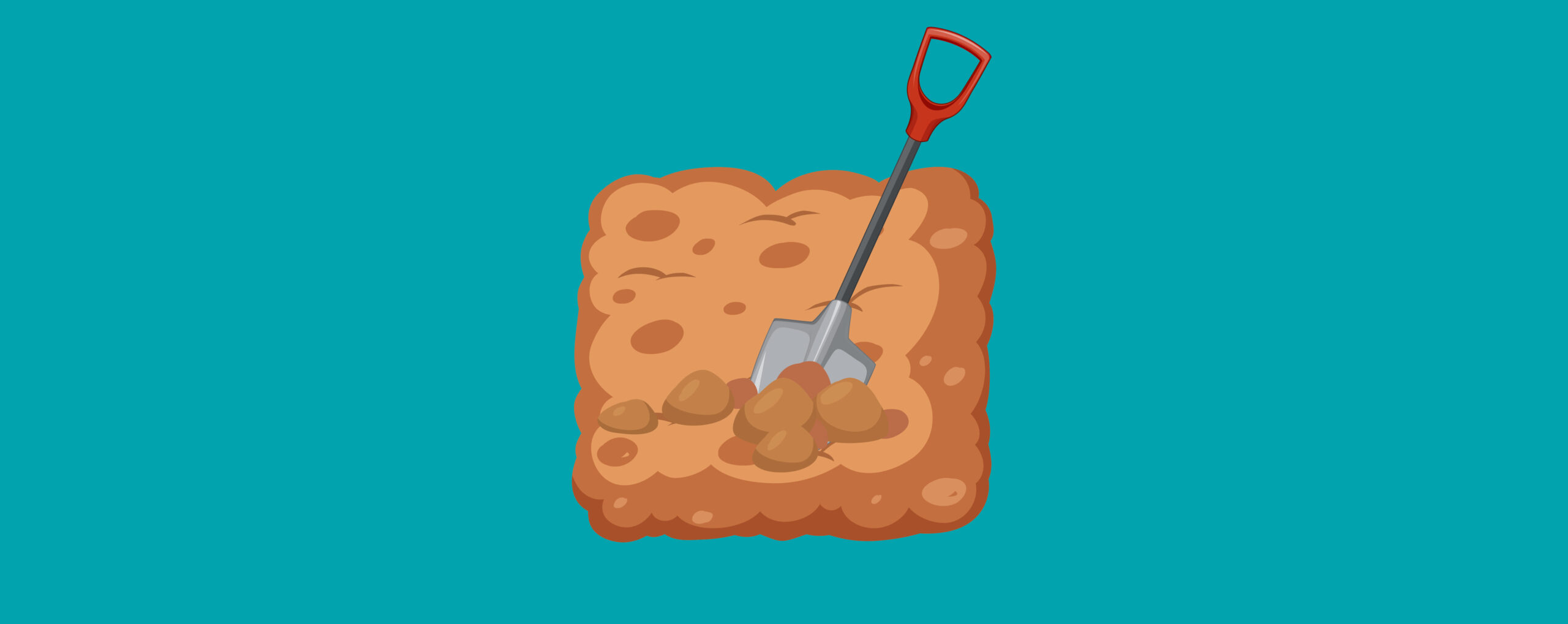
コメント