こんにちは。ikio(@ikio04731250)です。
実家の相続農地を使って「農業 × 商品開発」に挑戦中です。
農地も立派な資産。これも不動産投資(資産形成・活用)の一環として活かし、収益化するプロジェクトを進めています!
この取り組みの始まりはこちらの記事から。
▶「農業はじめました」不動産投資の新しい挑戦
早いもので、このプロジェクトに取り掛かって約半年。
サツマイモの定植が5月頭でしたので、10月末〜11月頭が収穫期になります。
今回は、その「試掘」の様子をまとめてみました。
収穫期の目安を確認
サツマイモなどの根菜類は土の中で育つため、実際には掘ってみないと確実なことは分かりません。
とはいえ、外からでもある程度判断できるポイントがあります。
■株元(つるの根本)の葉が黄色くなる
株元の葉5~6枚が黄色~茶色くなってきたら、収穫にちょうど良い。これが最もわかりやすいサインです。
■葉全体の勢いが落ちてくる
新しい芽やつるの伸びが止まり、全体的に葉がやや硬く、色もくすんできます。
■試し掘りで芋の皮がしっかりしている
手でこすっても皮が剥けにくければ完熟に近い状態です。
→これが今回掘ってから確認するポイントですね。
さて、それを踏まえて圃場を見渡すと(写真撮り忘れました・・)
・葉全体はまだ少し青々としている印象。
・株元の葉も黄化してないかな~?
・ツルは固くなってきているし、前回のツル返し後もあまり伸びていない。
つまり、地上部の勢いは落ちてきているようです。
あとは実際に掘って確認ですね。
試掘開始!
掘るときの手順はいたってシンプルです。
①マルチを一部だけ剥がす
全体ではなく、1〜2株分の範囲をめくる。後で戻す場合は破らず丁寧にめくると◎。
②ツルを株元で切る
地上部と芋をつなぐツルをハサミや鎌で切断。ツルは圃場の隅や畦外に一時避ける。(病気・虫が多い場合は圃場外に持ち出しが安心)
③株のまわりを20cmほど掘り返す
芋を傷つけないよう手か小さなスコップで慎重に。根の太り方も一緒にチェックします。
④芋の様子を観察
大きさ・数・皮の色・虫食い跡などをチェック。
・・と、手順だけなら簡単そうなんですが、実際にやるとこれがなかなか大変でして。
②ツルを株元で切る
→隣のツルと複雑に絡み合っており、試掘段階で特定株のツルだけ除去は無理でした。とりあえずそのまま放置。
③株のまわりを20cmほど掘り返す
→初年ということもあって土が固い!手では無理なので、鍬で一気に掘り上げます。
畝を低く作ったせいか、粘土層にまで根が伸びていて、掘り出すだけで一苦労です。
そして④芋の様子を観察
しっかり育っていてまずは一安心!
ただ、まだ少し小ぶりかな?表面を触ると皮もまだ薄い印象。もう少し成熟させても良さそうです。

試掘は「圃場中央部」と「北東の畝端」で行いました。
これは、一番育っていそうな場所と、日当たりが悪く育ちにくい場所を比べ、生育差を見るためです。
試掘の結果は?
以下の写真は試掘したサツマイモ。
赤いかごが中央部、黒いバケツが北東のものです。
中央部の芋は、形・太さともにちょうどよい食用サイズで、紅はるからしい滑らかな肌質が見えています。
一方、北東の芋はやや形が不揃いで、成長にムラが見られますが、サイズ的には十分。
■今の状態まとめ
葉の状態:まだ青いが、地中の肥大はほぼ完了段階。
表皮:ツヤがあり、しっかり紅色。→ 成熟度◎。
サイズ:まだ伸びしろあり。
形:きれいな紡錘形で締まりがあり、病害や虫害の跡なし。
予定通り、10月末~11月頭の収穫で良さそうです。
ただ、収穫予定日の前日には雨予報・・。
雨の翌日に掘ると、泥が重く・芋の表皮が擦れやすく・乾きが悪いので避けたいところ。
ですが、週末農家ゆえ、強行するしかなさそうです。まぁ頑張りますか!
ひとつ懸念点が・・
中央部の土を掘り返しているときに、奴らがいました。
そう、コガネムシの幼虫です!(写真は自粛)
この虫の被害としては芋の表面~中が食われて商品価値がなくなることです。
上の写真は子どもの保育園での被害例。
1cmほどの穴を開けられて、持ち帰り不可になったそうです。
「掘ってきたイモ、一口あげるね!」と嬉しそうに話していたので、ショックが大きそうでした。かわいそうですが、こればかりは仕方ありません・・。
こんな害虫が、ウチの圃場にも出たわけです。
2株ほどを掘り返した際に数匹+卵っぽいものが出てきました。
今の時期(10月下旬)では薬剤などの対策も難しいので、見つけ次第捕殺しかできません。・・まぁ結果絵的に無農薬栽培です。
ただ、幸いにも掘り出したイモは傷なしでした。
どうやらまだ株元の細い根を食べている段階のようで、イモまで被害が及んでいないようです・・良かった。
当初の予定では、サツマイモの後には落花生の作付け予定でしたが、この計画は見送る必要がありそうです。
コガネムシ類は概ね11月~3月の寒い時期を土中で越冬するとのこと。
そのため、この冬には畝を軽く耕して天地返しを行う必要があるでしょう。寒気と乾燥で幼虫・卵を死滅させる予定です。
育成を見送るのは残念ですが、結果的に来年の防虫対策の第一歩になります。
このあたりの対策は、また後日まとめたいと思います。
まとめ
サツマイモ育成もいよいよ最終段階です。
あとの商品販売までの工程は収穫後、少し乾燥させてから加工工場へ出荷するのみです。
あと少し、頑張っていきたいと思います。
今回は以上です。
ごほうびの芽→https://gohoubi.buyshop.jp/
ご感想・ご質問はお気軽に!
X(旧Twitter)→ @ikio04731250
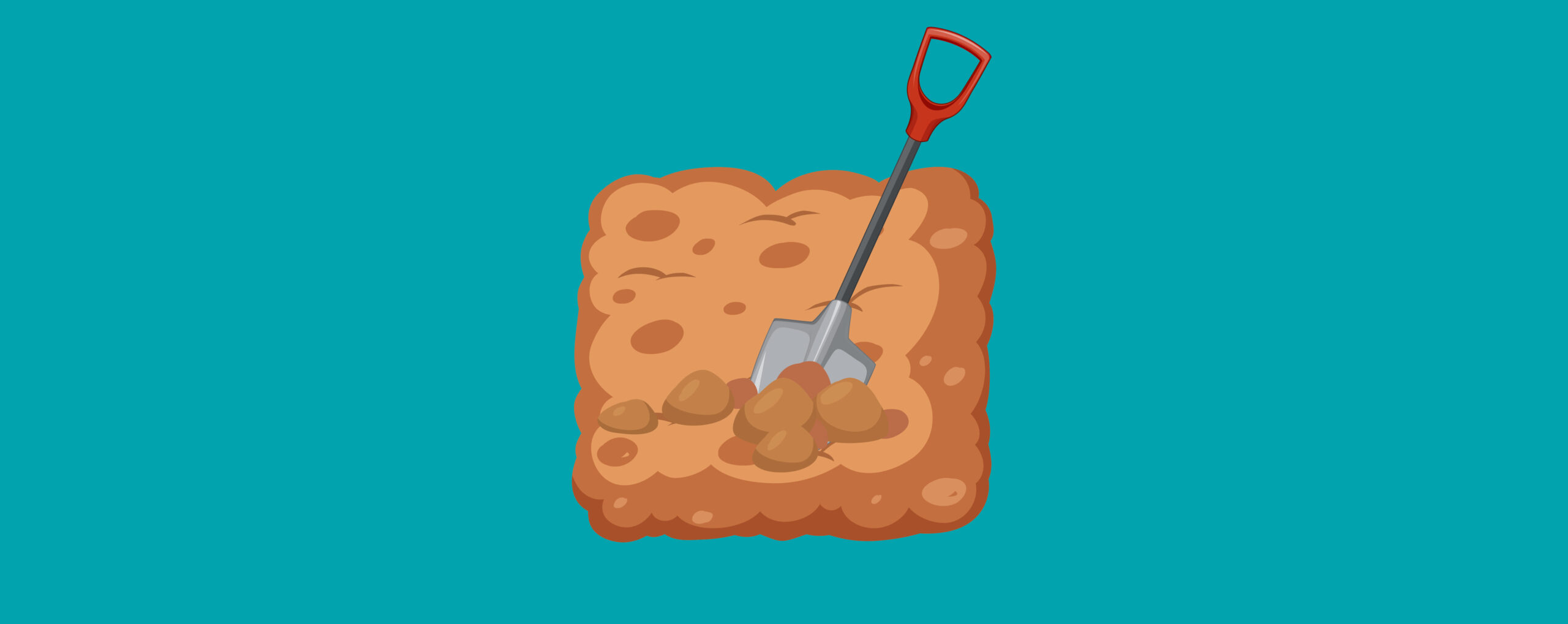
コメント