こんにちは。ikio(@ikio04731250)です。
不動産投資をやっていると、必ずぶつかるのが「この費用・・修繕費と資本的支出、どっちになるの?」という問題です。
SNSを眺めていても、「税務調査」や「リフォーム費用が資本的支出扱いになった(税務署から指摘あった)」など見かけます。
確定申告の時期になると、税理士さんに「これは修繕費でいいですよね?」と聞きながら仕訳をしている方も多いのではないでしょうか。
ここは気を付けないといけない、危険なポイントなんです。
税務調査で最もよく指摘されるのが「修繕費の過大計上」。つまり、本来は資本的支出として減価償却しなければいけないのに、経費に一括計上してしまうパターンです。
そんなに大事?と思われるかもしれませんが、現金の支出は同じでも、経理処理を間違えると税額が数十万円単位で変わることもあります。
「修繕費」と「資本的支出」の違いを正しく理解しておくことは、節税以前に自分を守る防衛策であり、逆にうまく使いこなせれば税金の調整ができます。
修繕費と資本的支出の違いをざっくり言うと?
言葉だけ聞くと難しそうですが、確認する点はシンプルです。「建物の価値や性能を高めているかどうか」。
これにより、修繕費か資本的支出か分けられます。
■修繕費
その年に全額経費にできる。
■資本的支出
減価償却で数年に分けて経費化する。
※参考:国税庁タックスアンサーNo.1379「修繕費とならないものの判定」
※外部サイトに移動します
例えば、モルタル壁の外壁塗装で1,000万円かかった場合・・
・修繕前と同等の塗料
→機能向上していない=原状回復扱いなので、まるごと修繕費で計上。
・より耐久性の高い塗料+タイルも貼った
→明らかに機能強化され建物の外観も豪華になっているので、資本的支出で計上され、建物自体の法定耐用年数(例えば鉄骨38年、木造22年等)又は新設部分の構築物耐用年数(15年等)に準じます。
この場合、ざっくりと毎年約26万円~66万円を減価償却していく感じです。
その年の家賃収入が1,000万円あったとしたら・・
・修繕費
→経費1,000万円を相殺して所得課税ゼロ
・資本的支出
→減価償却費26万円を相殺して所得課税974万円とすると、税金は約265万円(所得税+住民税)
このように、納める税金が大きく変わってきます。まぁ、もちろん利益がほとんど出ていなければ、どちらでも結果は大きく変わりませんが。
利益が大きく出たので、利益を抑えたい(節税したい)。もしくは将来的に節税効果を持ち越したい、など戦略的に利用することも可能です。
【クイズ】これは修繕費?資本的支出?
では、ここでちょっと実践。
次の3つのリフォーム費用、あなたならどう判断しますか?
■ケース①:原状回復のためのクロス全張り替え
前の入居者が退去し、タバコのヤニで壁紙が黄色くなっていたため、全室のクロスを張り替え。
床も少し傷んでいたので、一部を同程度のフローリングに張り替えた。
→あなたの答えは?
正解:修繕費
これは元の状態に戻すための支出です。新しく価値を上げたわけではありません。
例外もあります。
注意したいのは「購入直後にまとめて実施したリフォーム」の場合。
購入後、「運営できる状態にする大規模な改修」として見られますので、資本的支出で計上するのが妥当です。
■ケース②:屋根をスレートからガルバリウム鋼板へ交換
古い木造アパートのスレート屋根を、耐久性の高いガルバリウム鋼板に変更。
→あなたの答えは?
正解:資本的支出
先ほどの外壁塗装の例と同じですね。
この工事で耐久性や防錆性が上がっており、建物の寿命を延ばしています。つまり「性能アップ」とみなされるため、資本的支出扱いです。
このように、素材をグレードアップしたリフォームは基本的に資本的支出だと思っておきましょう。
■ケース③:古いエアコンの交換
古いエアコンを撤去して、自動掃除機能付きエアコン(約15万円)に変更。この際に設置費用は4万円かかった。
→あなたの答えは?
正解:全額経費と資本的支出を選べる
ポイントは、あなたが青色申告事業者であるかどうか。
購入費と設置費を合わせて20万円未満※1であれば、「一括償却資産」として3年間で均等に経費計上できます。
もしくは、一定の条件を満たす青色申告事業者(中小企業者)であれば、「少額減価償却資産の特例※2」を利用して、購入した年に「全額経費」として経費計上することも可能です。
※1:適用できない場合は、原則として6年(耐用年数)で減価償却します。
※2:特例を利用できる資産の合計額には年間300万円の上限があります。
税務調査で狙われる修繕費の落とし穴
税務署は「支出の目的」を重視します。
金額が大きい修繕ほど、「これは単なる修繕ではなく、価値を高める投資ですよね?」と突っ込まれやすい。
実際、修繕費の中でも100万円を超える「目立った」ものは要注意です。
修繕費と資本的支出の区別でよくあるトラブルは、「内容そのもの」よりも「書類の書き方」や「説明不足」にあります。
例えばこんなケース。
・見積書の品目が「リノベーション工事一式」になっている
・原状回復目的なのに「内装グレードアップ」などの文言が入っている
・領収書の金額が大きく、「一式◯◯万円」で内訳が不明
・空室期間中にまとめて改修しており、取得原価に近いと見なされる
こうなると、税務署は「資本的支出」として処理し直すよう指摘してくる可能性があります。
しかも過去分に遡って修正されるため、追徴課税+延滞税のダブルパンチを食らう、なんて場合も・・。
じゃあ、どうやって防げばいいの?という話ですよね。
次のような工夫でかなりリスクを減らせます。
・見積書・請求書の文言を意識する
「修繕」「補修」「原状回復」といった表現を使ってもらう。
「リフォーム」「リノベーション」「増改築」は資本的支出と見なされやすいワードです。(まぁ自分で説明ができるなら業者の書き方は何でもOKです)
・工事前後の写真を残す
Before/After写真を残しておくと、目的が修繕だと説明しやすくなります。写真はスマホで十分。
・項目を分けて請求してもらう
複数の工事をまとめて発注した場合、「修繕費」と「資本的支出」が混ざることもあります。
この場合は工事項目ごとに明細を分けることで、後から仕訳がしやすくなります。最低限、内訳は分かるようにしておくとGOOD。
・税理士に相談するタイミングを早める
不安であれば見積り段階で一度確認しておくのがおすすめ。「この内容なら修繕費にできそうか」を事前にチェックしてもらいましょう。
ちなみに、税務署に直接電話して確認するのもOKです。
「修繕費の計上タイミング」も落とし穴
もう一つ見落とされがちなのが、「いつ経費にするか」というタイミングです。
原則として、修繕費は工事が完了した時点で経費に計上します。支払日ベースではないので、工期が長いと年度をまたぐこともあります。
特に個人事業主だと12月決算なので、「年内に完了するかどうか」で経費化の年度が変わるため、注意が必要です。
時期によっては、工事を別口に分けるなどの調整が必要になります。
まとめ
修繕費と資本的支出の違いは、単なる節税テクニックではありません。これを知っているかどうかで、調査時の安心感も、日々の投資判断の自由度も変わってきます。
税務署は「どんな目的で支出したか」「それによって価値が上がったか」を見ています。
つまり、“目的”と“証拠”が一致しているかどうかがすべて。
判断に迷ったときは、次の2つの質問を自分にしてみてください。
・これは建物の価値を上げたか?
・建物の寿命を延ばしたか?
どちらかに「はい」と答えたら、資本的支出の可能性が高いです。
次にリフォーム見積もりを取るときは、ぜひ「この工事、修繕費にできそうか?」を考えてみてください。
修繕費の判断は、慣れないうちは本当に難しいんですよねぇ。
でも、事前に知っておくだけで「うっかり資本的支出扱いされる」リスクはぐっと減ります。
本記事のまとめ。
・原状回復なら修繕費。
・性能アップ・寿命延長なら資本的支出。
・書類と説明を整えて、税務署にツッコまれないようにする。
「経費で落とせるかどうか?」は、税理士任せにせず、自分でも理解しておく。それが、不動産投資を長く安定して続けるための基礎力になります。
今回は以上です。
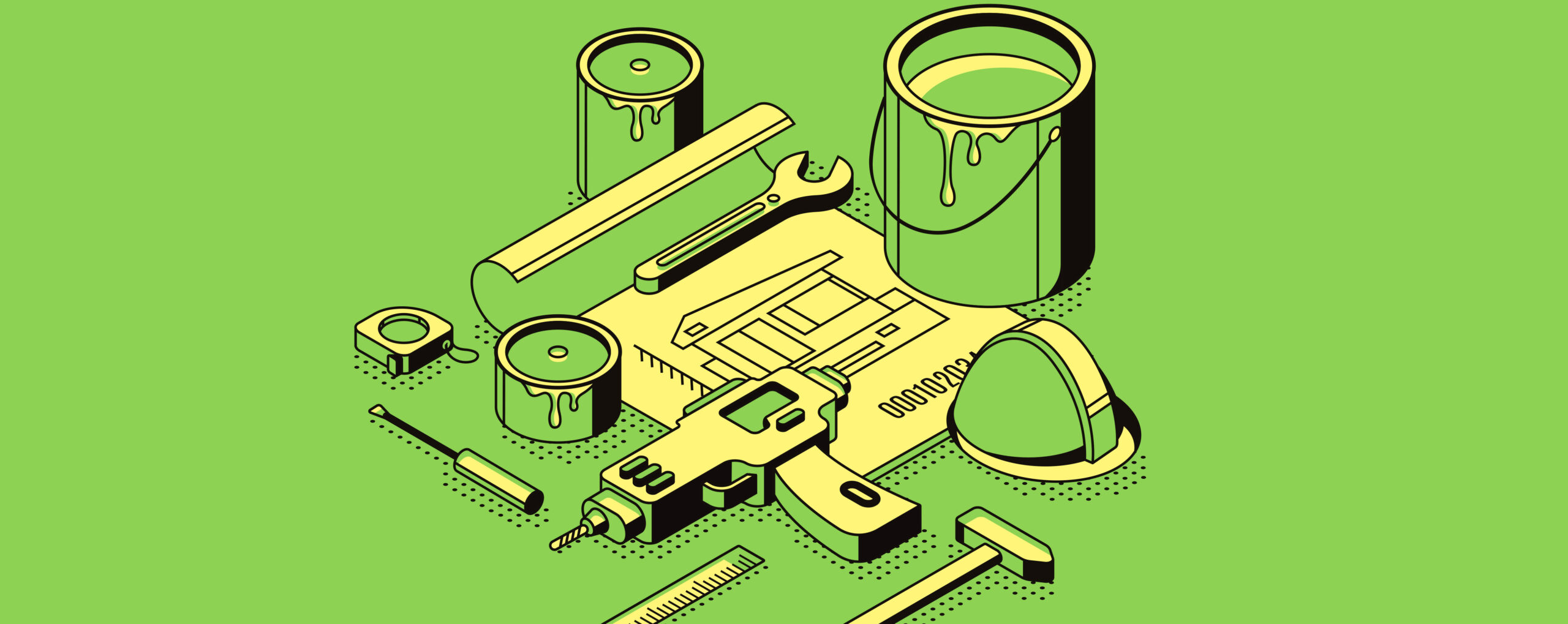
コメント